こんにちは。オクユイカです。
10月4日(木)にカラフルをオープンしてから10日が経った。
カラフルのHPは相変わらずまだ公開できていないし、個人的な気持ちなので自分の場所(ブログ)に書こうと思う。
オープンから10日。70名ほどのかたに来ていただいた。
昨日のカラフル初日。
広報も上手くできてないし誰も来ないわ〜と事務作業する気満々だったら80代のおばあちゃまが!コーヒーの注文をいただき…宝物の100円ができた😭
その後かわいいドラマーも♡
地域の方が自ら来てくださったことが嬉しすぎる!
今日も事務作業できず😆
※写真掲載許可済 pic.twitter.com/MaADxR79aD
— オクユイカ (@Saba0m) 2018年10月6日
オープンの次の日から何度も来てくださる方、ちょこっと立ち寄ってくださった方も含めて 70人ほどのかたがカラフルに遊びに来てくださいました。
アーティストさんが立ち寄ってくださったり、県外からきたまちづくり関係の方。
ご近所の方や友だち等々。

お互いを気にしながら遊ぶお子ちゃま。どのお子さんにも壁のホワイトボードは大人気!!!

同じ年代の方々が集まった時には「女学校の時はね」「○○町の○○さん、物凄く美人で有名だったわよね」等の昔話に花が咲いたり。

「お昼だからオニギリつくりましょう!」とみんなでご飯食べたり。
超ゆる〜いイベントも3回実施。
おばあちゃまと話をすると
「昔、近所の人にご飯食べさせてもらいよった」
「隣んばーちゃんによくしてもらった」
という話を聞く。
今で言う“こども食堂”かな。
そんな言葉を使わなくとも良い意味で昔の当たり前を取り戻したい。
昨日はカラフルで栗ご飯づくり!
2歳〜92歳で賑やかに。 pic.twitter.com/n01vk8ICr2
— オクユイカ (@Saba0m) 2018年10月8日
週に2度のイベントは竹田市高齢福祉課の「介護予防・ささえあい事業」の助成金申請をしていて、条件が揃えば光熱費代などが出るようになっています。
- 65歳以上が半数
- 65歳以上が5人以上
が大きな条件で、これをクリアしないとカラフルの収入源はほぼ無し。
大きな金額ではないものの唯一の収入源です。人数の面では3度ともクリア!
カラフルのオープン前にご近所の方に事前説明会をしたことで、ご近所さんが参加してくださったのが大きいと思う!!
また、敢えて「超ゆる〜いイベント」にしているのは”受け身”で来ていただくよりも、”一緒につくる”イメージにしたかったから。
例えば今日は「餃子を作って食べよう!」というタイトルはつけたものの、餃子の作り方は知らない状態でスタート。笑
知っている方がいるからその方から学べばそれでいい!
実際、作り方を紙に書いてくださったり自家製ニラを採ってきて提供してくださったり
足りない材料は、お子さんと手を繋いで買い物に。
「あれ?餃子のタレは?!酢? 酢はないからまた買いに行く?!」
「カボスがあったら酢のかわりになるよ」
「あ!カボスは昨日いただいたものがある!!」
って、なんだかんだで解決をしたり、うまい具合に連携ができていく・・・
これは、竹田だからこそだと思う。



ただし、発達障がいのある方の中には「見通し」があることで安心できる場合もあるので、その点は参加する方に合わせて対応していきたいと思います。
今後の課題はめちゃくちゃあるけれど、
「赤ちゃんからご高齢の方まで、障がいの有無に関わらず」
そんな場所にはなっていたのかも。
「電気ポットかわなきゃ」
「うちに余っているのあるからあげるわ~」
そんな場面が多々あったり
「あ、靴ベラがないね」
と会話した次の日に、靴ベラが玄関に置いてある・・・。
やっぱり、ここは優しい町だなって感じました。
そして相変わらず事務作業や広報は進まず・・・笑
というより少しずつ進めているものの、集中ができないんですよね。
想像以上のインプットや学び、出会いがありで、そのことが頭の中をグルグルしていたからだと思います。
また、現時点で「福祉」について困っている方からのご相談なども何件かあり
カラフルとしてできることはなんだろう?と真剣に考えてみたり。
そんな10日間だった。
今後の課題をざっと書いてみる。
「福祉」「障がい」という言葉に対する心理的距離を無くしたい。
関係ないと思っている方にどう自分事と感じてもらうようになれるか?を考えると
相手を知る機会をどう作るか。です。
興味ないことを ”わざわざ” 知ろうとなんてしないわけで、”たまたま知った” が大切ですよね。
福祉施設だと感じた瞬間に避ける人もいると思うので、そう思われない工夫が今後さらに必要になると思います。
「障がいのある子どもが生まれた=恥ずかしい・隠さないといけない」と思う方も、周りの支えがたくさんあれば、少し気持ちが楽になりますし、
普段から顔なじみの関係ができていれば保護者の方が困った時に「ここに相談しにいこう」ってなると思うんです。
そういった雰囲気作りが障害のあるお子さんの早期発見・早期療育にも繋がると思います。
だからこそ、福祉施設だと思われない工夫が必要。
1年間は「福祉」「障がい」という言葉に対する心理的な距離を縮めることに焦点を当てたいと思っています。
ただ、現時点で困っている方(福祉)のお話をお伺いすると、内容は違えど
「居場所」が無いことが課題になっていることもわかった。
特に、マイノリティの方の中のマイノリティになるとね。
それにはできる限り早く対応できるようになりたいと思うんです。
だって
こんなに1人で抱えてがんばってらしゃったんですね〜。。。。涙
って感じる相談が多いんだもん。
地方は選択肢が少ないことも課題。
でも「都会にはあるけれど、地方にはない」っていうのは寂しいことなので、地方でもうまい具合に対応できる方法を考えたいと思います。
マイノリティでも生きやすい場所づくりができたらいいな。
というわけで・・・!!
全てをすぐにはできないので長期的なスパンで物事を考える必要があるんだけれど、
継続して活動するための収益をどうするか?も課題。
・・・・あとは、自分自身の脳みそをスッキリさせないと。ごちゃごちゃしずぎ。
マニュアル化できない「対 ひと」の部分に心くばりができるように
マニュアル化できる部分はマニュアル化して、無駄な動きを減らす工夫をしないといけないと強く感じてます。
人手が足りないのは仕方ないので、その中でどうサボるか・・・・というと聞こえが悪いけれど
自分自身の心の状態を保つために「何に重点を置くか」ってところですよね。
最初は上手くいかないのが当然だと思うので
実践から見つけた課題に対応しながら進みたいと思います。
ただ、「場」としての需要はものすごく感じたし幸先良いスタートになったのは
一緒に考えてくださるメンバーやご近所の方、応援してる仲間のおかげ!
そしてそして大分市や熊本からわざわざお立ち寄り頂いた友だちにも感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました。
そしてこれからもどうぞよろしくお願いしますm(__)m
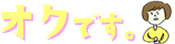









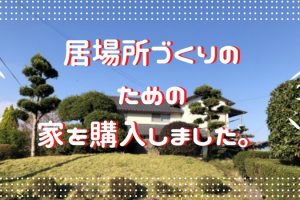


コメントを残す