こんにちは!竹田市地域おこし協力隊のオクユイカ(@Saba0m)です。
- 保育士の仕事に興味がある。
- 保育士になりたいと思っている。
今回はそんな方に向けた記事です(^^)
といっても、私は保育士ではないので、保育士さんに寄稿していただきました♪♪
給料はどうなの?仕事は大変?!やりがいは?!
仕事内容の前に、気になることについてぶっちゃけトーク!
目次
保育士ぶっちゃけ質問コーナー
Q、保育士って忙しいの??
A、場所や形態にもよると思いますが、私は私立保育園の正職員でフルタイムだったので、本当に忙しかったです。。。
園は、残業しないで早く帰宅しなさいというけれど、じゃあ、いつどこでこの仕事をするの?
って、結局お持ち帰り仕事でした。
ただ、朝だけ、夕だけといった短時間パートやアルバイト、非常勤職員など働き方(給料も)は様々だと思うので、自分に合ったものを選ぶといいと思います。
登録無料でお祝い金ももらえる!保育士の転職ならジョブメドレーQ、保育士の給料は安いの??
A、一言でいうと、あれだけの労働時間、専門性にたいして、安い!と思います。
昔、保護者のおじい様に
「こどもと遊んでるだけでお金もらえていいなぁ~」
っと言われたことがあり
“そんな風に見えるんだ”とショックだったことがありますが
大切な命をあずかる、それぞれが心をもつ“人”と向き合うお仕事。。。
そんな簡単なわけがありません。
発達や心理学、人権、幼児体育、音楽など、それらを学ぶだけでなく、勤めてからも研修に出かけたり、本を読んだりと常に勉強です。
「こどもと生活をする」ということには様々な努力と想いから成り立っていると思います。
私が勤めていた保育園はどの職員もこどもが大好きでやりがいを感じながら働いていました。
愛のある職場で人間関係も良く、休みがとりやすかったり、助け合えたり、といった恵まれた職場でした。
(そりゃ、ちょっとくらいの意見のぶつかりあいや誤解はちょこちょこありますが)
ただ、その分、先生がたの人間性でなりたっていた部分も多いです。
タイムカードを押してからサービス残業していたり、休日に行事出勤しても代休がなかったり・・・理不尽なこともありました。
少しづつですが、やっと世の中で保育士の処遇改善が言われはじめて、加算金がでたりしていますが、根本的なところはまだまだです。
健康的に気持ちよく働くことができるよう、これからに期待したいですね(*^^*)
保育士の仕事内容
保育士の一日について
ではでは、保育園での保育士の一日について書こうと思います。
小さいころ、先生たちと過ごした記憶って覚えていますか?
絵本をよんでもらったこと
一緒に鬼ごっこをしたこと
給食を隣で食べたこと
叱られたこと
抱っこしてくれたこと、、、。
そんな先生たちは、実際にどんな仕事をしているのでしょうか。
ここでは保育士=先生として書いています。
子どもたちが登園する。

私が勤めていた保育園では7時半から18時半の間にいくつかのシフトがありました。
ここでは例として8時半から16時半の場合を紹介します。
登園してきたこどもたちや保護者の方に挨拶をし、その日の様子を聞いてやりとりします。
いろいろな話が聞けてすごく楽しい時間でもあります!
それと同時に話をしながら
‶いつもより身体が熱いかも″‶あくびをしてるから眠いのかな″‶少し言葉が少ないからお疲れかな″
など表情や機嫌を含め、その子や保護者の気持ちを感じるようにしていました。
もちろんすべてではありませんが、特にこどもは朝に
“いつもと何か違うなあ”
と感じた時は、その後に熱がでたり、体調を崩したり、、、と何らかのサインであることがあります。
保護者の方には笑顔で「いってらっしゃい」をして、お仕事に出かけてもらいます。
こどもでも大人でも、一日の始まりは心地よくいたいものですもんね!
なにより保護者の方にとっては大切な我が子を預ける人であり場所です。
毎日の笑顔が信頼関係につながっていくと思っています。
朝の活動

7時半から開園しているので順次登園(^^)
登園してきたこどもたちと関わりながら、個人の連絡ノートをチェック!!
その日の体温、ご飯、睡眠、様子、送迎の人などを把握し、全職員に伝える必要のあるものは朝礼で報告。
朝に全員が保育から離れることはできないので、集められた情報が書かれた朝礼ノートを、順番に見るようにしていました。
そこからそれぞれのクラスで活動がはじまります♪
いくつかのコーナーに分かれて自分の好きな遊びをしたり、絵の具やクレパスで自由に表現したり、
散歩や公園に出かけたり、鬼ごっこ、新聞紙遊び、触れ合い遊び、空き箱制作、夏にはプールも!!
まだまだ、もっともっと楽しいことがいっぱいです。
ひとりひとり、好きなことや苦手なことは違いますが、
その子にとっての“楽しい”“うれしい”“わくわく”が見つかるように、、、
どこかで自分を表現できるように、、、。
そのために、いつもこどもたちのことをよく見ておくことが大切でした。
そのうえで、静と動のバランス考えて、できるだけ偏らないように活動内容を考えて準備します。
あとは先生たちも思いっきり楽しもう!!!(^^)!
わりと思ったことをどんどんやってみようという自由な園だったのであれこれと挑戦できて楽しかったです。
排泄

生活の中で欠かせない排泄。
活動の前後に声をかけたり、その子に合わせてやり方を伝えたりします。
小さい子は個々に合わせて、おしめを換えたり、だいたい1歳児クラスではトイレトレーニングもはじまりますね。
排泄は生理的なもので発達や個人差もあるので、その子に合わせて、保護者と連絡をとりながらが前提。
こどもや保護者の気持ちをおもいながら、一緒に考えて進めていくといいのかなと思います。
排泄するとすっきり心地良い、、を感じてトイレですることが身についていくようにと思いながらトイレに誘うのですが、2歳児さんの時は本当に大変でした。。。
イヤイヤに加えて、お尻丸出しで走る走る。。。
そのうちどんどん楽しくなって、いつの間にかクラスが裸族だらけ、、、なんてこともありました!!笑
新人の頃は、こどもたちのが一枚上手!
きっと「あの先生、本気で追いかけてくる♡」なんて思われながら、完全に遊ばれていましたね( ;∀;)
先輩に聞いたり、経験を重ねていくうちに、“なぜイヤイヤというのか、どうしてそうなのか”を考えて対応するようになりました。
給食の時間
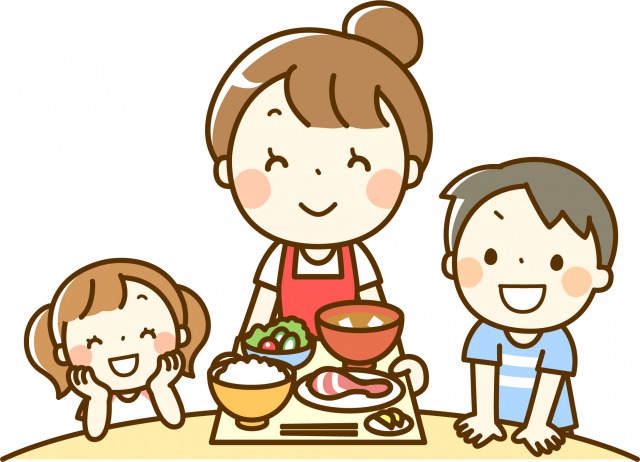
給食は多くの子どもが楽しみにしている時間です。
私の保育園では給食室で作ったものを先生が配膳していきます。(0歳児はそれぞれにあった離乳食)
こどもたちの年齢に合わせて一定量を目安に盛り付けますが、その子によっての配慮も必要です。
例えば、野菜が苦手な子にはたくさん入れるよりも、少しでも食べられたという満足感を味わって欲しいので
少量にして様子を見ながらすすめます。
たくさんの食材に触れてほしいという思いもありますが、まずは食事の時間を少しでも楽しいと感じられればという思いもあるからです。
アレルギーを持っている子は毎日、給食の先生とその日のメニューについて確認をし、専用のトレイにいれて担任同士、直接声をかけあうようにしていました。
3,4,5歳児になると、年齢によってできることを当番活動として給食の準備をします。
机を拭く、食器を並べるなど、こどもたちはとても楽しそう!(^^)
一緒に準備をしながら、並べ方を伝えたり、“どうやったらおいしそうかな?”とともに考えたり、
机拭きの後はこっそりフォローしたり、食器を運ぶ姿も危険がないかみたり、、、
目も手も心も動かしっぱなしです。
小さい子は準備している間にも、じーっと座ってることなんてないですよね。
なので、もう一人の先生が絵本を読んだり、歌を歌ったり、手品をしたり、、いろいろと惹きつけて楽しく待てるようにしていました。
さらに給食後のために歯ブラシを洗って並べたり布団をひいておいたりパジャマを準備したりもあります。
3歳児から一人での担任になると、それもできなくなるので本当にバタバタでした。
さあ、やっとこどもたちと楽しい食事時間!!っというのもつかの間
「先生、みそ汁こぼれたぁ~」
「おしっこでちゃった。。。」
「おともだちが笑ってくるのいや~」
などなど、あちこちで声がかかります。
ほんとゆっくり食べるなんてことは、ほぼ無理ですね。。。
でもそんなことも、こどもたちとの大事な生活の一部でした(^^)
午睡(お昼寝の時間)

給食後は歯磨きをして、パジャマに着替えて午睡にはいります。(4,5歳児は午後も活動です。)
パジャマに着替えるのも、こどもたちはそれぞれで様々な姿がたくさんみられます。
なんとか自分でボタンをとめようとしていたり、先生に着替えさせてほしかったり、
ズボンを着ようとしていたり、振り回してともだちとケンカしたり、身体に巻いてお姫様に変身していたり・・・
そんな姿を見ながらもひとつずつ対応していきます。
部屋の照明を消してからは、少しでも安心して眠れるように、身体をさすったりトントンしたり素話を。
つかの間の静かな時間です。
それでも体力があって眠らない子、物音に敏感でなかなか寝付けない子など、その子それぞれなので、できる限りその子に合わせた対応が必要です。
いつまでも側でトントンしてあげたいのですが
ある程度寝付くと
- 給食の片付け
- トイレ掃除
- 汚れ物を洗ってそれぞれのかばんになおす
- 荷物作り
- 手紙をいれる
- 個人のノートにその日の様子や食事量、午睡時間などを書く。
など、やることが沢山あります!
特に、個人のノートにその日の子どもの様子を書くと、「こどものことがよくわかる!」「見るのがうれしい!」と、保護者の方はとても楽しみにしてくださっていました。
私自身も保護者とのやりとりが楽しくて、忙しくて書けないこともありましたが、できるだけ大切に書いていました。
文章が苦手な人も少しずつ慣れていくと思いますが、普段から本を読んだり、手紙を書いたりしていると良いと思います♪
そしてこの隙間をぬって交代で休憩をとっていきます。
先生たちと話をしたり、ホッとひといきお茶を飲んだり
気持ちの切り替えや交流に大切なひとときで、こんな時だからこそ相談ができたり、気軽に話せたりするんですよね(*^^*)
ただ仕事が多くなかなか休憩に時間がとれないこともよくありました。
こどもたちと丁寧に向き合うためにも、先生たちが休憩をきちんととれる環境であってほしいなと思います。
おやつ

15時ごろから嬉しいおやつです♪
準備などは給食の時と、ほぼ変わらないです。
私の園では、できるだけ手作りおやつをいれていて、蒸しパンやホットケーキ、ラスク、ゼリー、マカロニあべかわ、キャベツ焼きなどなど
こどもたちの大好きなものがいっぱいでした!
月に1回給食ミーティングをしており、現場の保育士と給食室との間で
何が人気があるのか?大きさや固さはどうか?彩りや季節感は?味つけは?
と感じたことを話し合って、日々の食事に反映させるようにしていました。
だからほんとに美味しいんです(*^-^*)
おかえり
2~5歳児は一日の終わりに、今日あったことを話したり明日の連絡をしたりします。
こどもたちが明日も楽しく来ることができるように、さようならをします。
ここで個別にケガや体調不良、連絡があるこどものことを、もう一度確認し
夕方の延長保育の担当者に引き継ぎます。
簡単なものは個人の連絡ノートに書いたり担当者に任せますが、経緯が複雑なケンカや担任から伝えたいものなどは、保護者がきたら呼んでもらうようにします。
この連絡も保護者との信頼関係にとても大切でした。
夕方の活動(延長保育時間)

16時からは順次降園です。
お迎えがくるまでは0,1、2歳児は室内で、3~5歳児は園庭→室内で自由遊びをします。
異年齢で過ごす時間なので、どの年齢でも楽しめる遊びを準備したり
異年齢が自然にかかわれるように見守りながら、必要に応じてその場にいるようにしたり、クラスとはまた違った配慮が必要になります。
小さい子は大きい子のしていることをみて“やってみたい!”と興味をもったり憧れたり
大きい子は小さい子のお世話をして自分に自信をもったり・・・
覚えてほしくないなぁと思うような言葉も覚えたりもしますが(笑)。それよりも素敵ななにかが生まれる時間だとおもいます(^^)
その他の仕事内容
掃除
こどもたちが生活する場所なので掃除は毎日します。
室内は掃除機と床拭き(0歳児は床消毒もしていました)、手洗い場、トイレ掃除など。
ただ、保育園は開園時間中ずっとこどもたちがいるので、掃除にも一工夫。
園庭にでている間に室内を、室内にいる間に廊下をなどと、こどもたちに移動してもらっている間にしていました。
書類の記入
書類だけでも目まぐるしいです。
(「書類の記入はしなくてもよい」という条件で入っているパートさんもいます)
- 年度の始めに一年間のカリキュラム
- 月末には翌月の月間カリキュラム
- 週末には翌週の一週間カリキュラム
- 個人記録簿(0~2歳児は毎月、3~5歳児は学期ごと)
- 0~2歳児は毎月その子に合わせた目標をたてる個人表。
ほかにも、月一発行の園のたより、週一回している縦割り保育ノートや特別な支援が必要な家庭を対象とした個別支援計画などもありました。
行事、企画
こいのぼり、七夕、運動会、制作展、発表会、など様々な行事や季節事があります。
そのためにこどもたちの姿をみて、担任が企画発案を考えます。
例えば、七夕であれば
どのようにこどもたちに伝えるか?
どんな飾りを作るのか?
どんな素材に触れてほしいのか?
行事によっては早ければ2ヶ月前から考えたり見本を作ってみたりします。
この企画がたてるまでがとっても楽しいしんどい楽しい!!
いろいろ調べたり、こどもたちをもう一度よくみて本当に楽しめるのかを考えたり
ミーティングで各クラス出し合って話し合いをしたり。
それぞれの先生のカラーがでるなぁっていつも思っていました(^^)
教材準備
日々の保育で楽しむためには、準備が必要です。
絵の具をするのであれば、紙を切ったり何色を使うか考え、
その日には濃度を確かめたり、制作をするのであれば、はさみやのり、材料を用意しておきます。
もちろんすべて用意しすぎるのではなく、こどもたちと一緒に“何してあそぼう?”から考えて発展していくこともありますし
他のクラスでやっていることを真似たくて自然とあそびが始まる場合もあります。
普段からこどもたちの“やりたい!”“やってみたい!”を見逃さないように心がけていました。
会議、ミーティング
月に一度、全職員での会議、未満児クラスと以上児クラスに分かれてのミーティングがあります。
- 各クラスの連絡事項
- 全体で確認すべき危機管理のこと
- 気になる子についての対応の
- 疑問や悩み
等々、その時々によってバラバラです。
保育においての自分の意見を出し合い、こどもたちにとってのより良い保育にむけて話し合う時もありました。
委員、係の仕事
園全体のことをそれぞれで担当している仕事もあります。例えば、、、
貸出係
貸出の本やDVDを管理するために、貸出ノートをチェックしたり季節に合わせて入れ替えたり、注文したりする。
教材係
足りなくなった教材を整理、チェックし、事務室に連絡したり、新しい教材をとりいれる。
えんのたより委員
毎月発行のたよりの原稿を各クラスや原稿担当者から集めたり管理し、それを刷ってとじていく。
他にも屋上の整備や音楽、体操の係などなど、みんなでわりふっていました。
クラス懇談会、個人懇談会、保護者対応
年2回クラス懇談会があり、クラスの保護者と担任で顔を合わせて話す機会があります。
★5月の懇談会では、保護者同士の顔合わせやこれからのクラスの目標や取り組みについて、質問やフリートークをします。
ここで保護者同士も少しつながるといいな~と願いながら(^^)
★9月~12月の間には、年1回の個人懇談会をもうけていました。
保護者と1対1でゆっくりと話す機会です。
普段はなかなかゆっくり話せないので、家庭のことやこどもたちの家での姿など知り、これからにつなげるいい機会でした。
普段は忙しくて挨拶だけになりがちな保護者も、個別に話すとまた新たな一面を知ったりしてとても楽しい時間でした。
保護者から質問や相談があった時は、時間をつくってお話をきかせてもらいます。
直接、顔を合わせたほうが、表情もあり気持ちのやりとりがしやすいので、その時は勤務時間がおわっても保護者がお迎えにこられるまで待っていました。
保育士資格で働ける場所は?

今は幼保一元化や新制度が始まったこともあり、幼稚園や保育園だけでなく、こども園や保育ママなど、就学前のこどもたちが過ごす場所は様々。
また、保育だけでなく、以下の施設でも保育士の求人があります。
- 乳児院
- 児童養護施設
- 盲児施設・ろうあ児施設
- 肢体不自由児施設
- 知的障害児通所施設
- 重症心身障害児施設
- 放課後等デイサービス
- 母子生活支援施設
同じ資格であっても、仕事内容が大きく異なることもあります。

これから保育士になろう!と考えている学生さんや社会人の方は、”仕事”として子どもと関われる様々な現場に入って経験してみるとよいと思います。
保育や福祉関係も含めた求人情報が多く掲載されているのがジョブメドレー。

職場によって、働きやすさ・働きにくさというのは必ずあります。
私の職場は、人に恵まれているので働きやすかったです。
登録無料でお祝い金ももらえる!保育士の転職ならジョブメドレー
自分に合う職場がみつけることが大事だと思います。
![]()
最後に。保育士はやりがいがあるものの、忙しいです。
それでも想いを持って続けている保育士さんも多くいます。
よい職場との出会い、人との出会いがあることを願っています(^^)
ではでは!!
合わせてよみたい
- 半額クーポンが今だけ!→資生堂なのに激安!「レシピスト」の日焼け止め・化粧水・リップのセットが790円。半額クーポンをゲットしよう。
- 自信がない人に全力でオススメ→驚くほど当たると噂の無料長所診断やったら自信をもらえる!
- これは必見!→Amazonプレミアムがお得過ぎてビビるので紹介する。まだ入っていない方はお早めに!
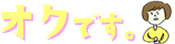

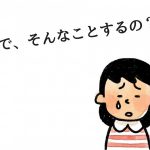
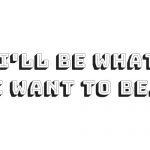

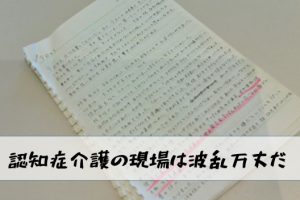






レクリエーション担当だけでなく、入浴介助や食事介助等の介護の仕事も一緒にしてた!