「おくちゃんには、予定時間の10分前の時間を伝えないといけないね」
って、今朝、恋人に言われました。
こんにちは、オクユイカです。
日本って時間に厳しくないですか??
なんで厳しいのかって気になったことありませんか?
気になりすぎるので、今日はそのことについて書きたいと思う。
※協力隊の訓練で「日本人研究」というのがあり私たちのチームがテーマとして取り組んだのが
「なぜ、日本人は時間に厳しいのか」ということ。これは、その時のまとめ記事です。
目次
日本も時間にルーズだった?!
この国ど~こだっ??
さて、この国ど~こだぁ??
新しい年の挨拶まわりだけで二日間を費やす国ど~こだぁ??
まるで協力隊員が派遣されるような国のお話のようですが、
実はこれらはすべて
明治時代以前の日本の話なんです。
1857年に長崎軍電伝習所に滞在していたウィレム・カッティンディーケという人がこのような事実を書き残しています。
「日本人の悠長さといったら呆れるくらいだ」
ってね。笑
今は日本の鉄道は世界一正確に運行しているし、腕時計を身に付けたり携帯で正確な時刻を確認しながら生活していますよね。
ちなみに、腕時計が普及したのは昭和時代。
1964年に普及率97%を超えました。
何分から”遅れ”になるの?
時間に厳しい国、日本。
実際に、このようなデータがあります。これはどのくらい列車が遅れたら遅れを発表するかという各国の比較です。
日本:1分以上遅れたら「遅れ」
フランス:14分以上遅れたら「遅れ」
イタリア:15分以上遅れたら「遅れ」
イギリス:10分以上で「遅れ」
フランスは14分・・・・だけれど、日本は1分以上遅れたら「遅れ」と発表されます。
一分違わず正確に運行する鉄道は今のところ世界でも稀。
また、それを当たり前のように求める社会も、それを当然の使命のように感じて非常に強い意志を持って追求してきた鉄道も世界では希です。
いつから時間を守るようになったのか。
江戸時代に遡ります。
江戸時代(17世紀中頃から18世紀にかけて)時鐘システムが誕生しました。
これが城門の開閉の時、登城の時、休息を知らせる役割を果たしていたんです。
そのため、必然的に城に仕える武士も時刻によって自らの生活を律するようになった。
時計を持っていたのは大名や豪商だけ。庶民は鐘の音で時刻を知っていたそうです!
しかし、この鐘も一日に数回しかならないので、江戸時代の人々は今の私たちのように分単位で時間を気にして生活していた、とはいえませんね。。。
よく聞いてくれたな、ミカンちゃん。さすが私の孫だ。

不定時法だった江戸時代
一日の長さを等分に分割する時刻制度を「定時法」といい、現在24等分した方法が日本だけじゃなく、世界中で使われています。
これに対して、一日を昼と夜に分けそれぞれを等分するやり方が「不定時法」!!
不定時法とは昼間の時間と夜間の時間をそれぞれ6等分して時間を計測する方法。
今に比べるとだいぶ、大雑把ですね!

この方法で認識できる時間の精度はせいぜい30~40分くらいでした。
(丑三つ時とかっていう言葉は、不定時法で使われていたもの)
明治時代に不定時法から定時法へ。
明治5年12月3日に定時法を取り入れてから「分」という
短い単位での時間概念を人々は知ることになりました。
鉄道と学校教育が時間に厳しい日本をつくった。
定時法が取り入れられたものの、新しい概念を取り入れることはそう簡単なことではなく、
時間が来ると出発する陸蒸気に一般庶民は戸惑い、乗り遅れていた人もかなりいたそうです。
ですが、この鉄道が人々の時間に対する意識をおおきく変えるきっかけになりました。
そして、人々の時間感覚の変革に大きな影響をもたらしたものがあります。
それが、教育。
教育の中で時間についてとりあげるようになったんですね。
なぜかというと・・・
時間をかけて教え込むのが定時法を普及させる一番確実な方法だからです。
どのような考え方に基づいて定時法を普及させてたかを簡単に言えば、
”優れた人物になりたいのなら勤勉になりなさい”
ということである。
毎日規則正しい生活を送り、寸刻惜しんで絶えず学び、その長年の蓄積によって優れた人物になり、
学問なり芸術(あるいは軍事)において立派な業績を築くことができる。
勤勉こそまさに明治の小学校教育が採用した思想であり、寸刻を惜しんで絶えずに学べば立派な業績を築ける、という教えでした。
日本が発展するためには時間に厳しくなる必要があった。
これといった資源もない中で、豊富で安価な勤勉な若い労働力と、旺盛な消費意欲を持った消費者を背景に、
いかに効率的な大量生産・大量消費の仕組みを作り、
より多くのモノやサービスを社会にいきわたらせるかという量的拡大に関するものを追い求めてきた。
これが、明治から昭和の高度経済成長が終わるまでの約100年前までの話。
30数年前ごろ~現在
高価な労働力と高齢化する人口、多様化する価値観やライフスタイルの下で、
いかにして社会に活気をもたらし、人々にゆとりを実感させるかという質的充実に関するものを模索しています。
お金よりもゆとりを大切にしたいという考え方にかわりつつあるのかもしれませんね。
確かに、お金も大事だけどゆとりも大事ですね、先生。
でもあの人無職だから、この先心配だわ。。。
以上、時間についてでした。成果も残したくて、ゆとりも持ちたいというワガママな私の今の課題はタイムマネジメントです(泣)
おすすめ本
遅刻の誕生 という本の中に、上記に書いたような昔の日本のこと等々が書かれています。
もっと詳しく知りたいというかたは、読んでみてください。
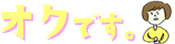
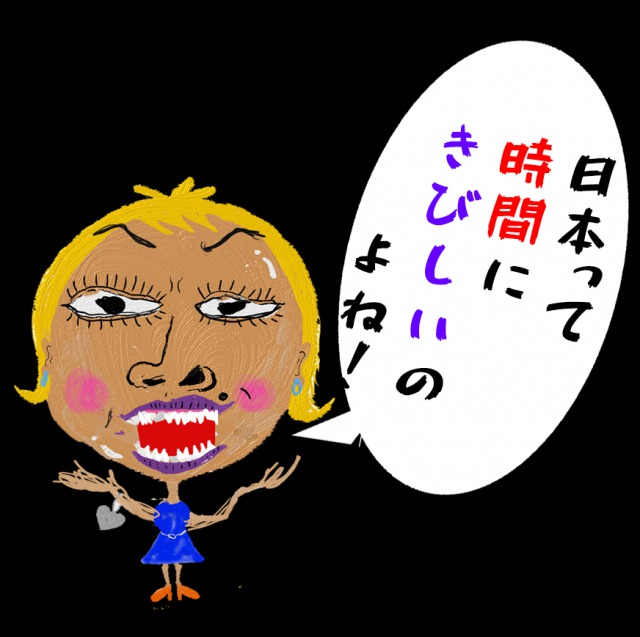
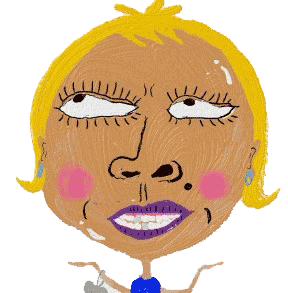



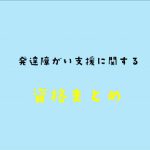



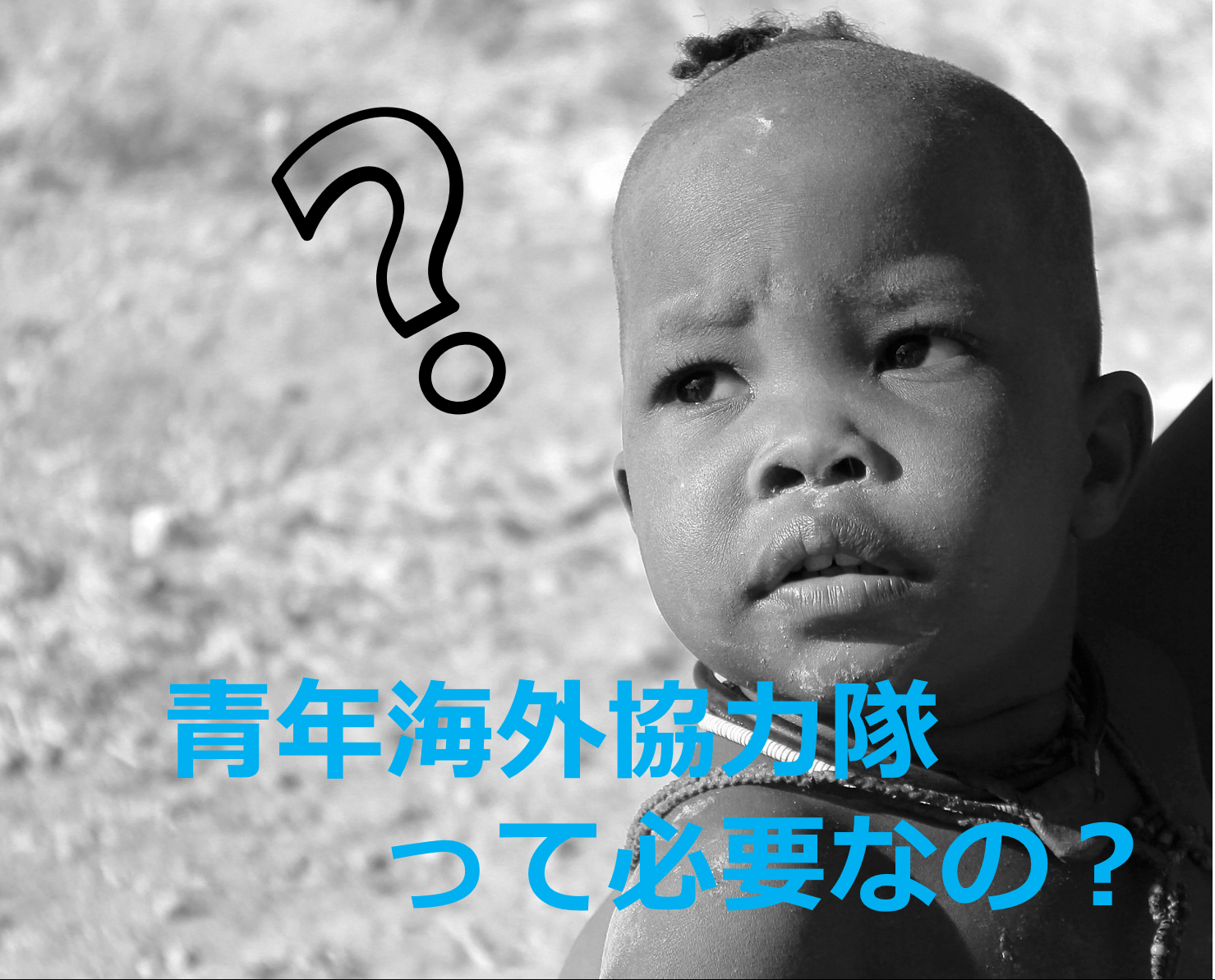





コメントを残す